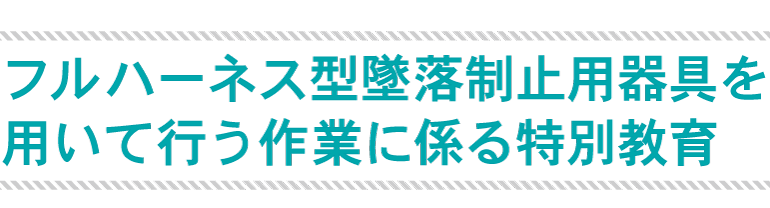フルハーネス型安全帯の使用には「特別教育」が必要になります
2019年2月1日より、労働安全衛生規則の改正により墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務※を行う労働者は、特別教育を受けなければなりません。
※特に危険性の高い業務・・・高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務
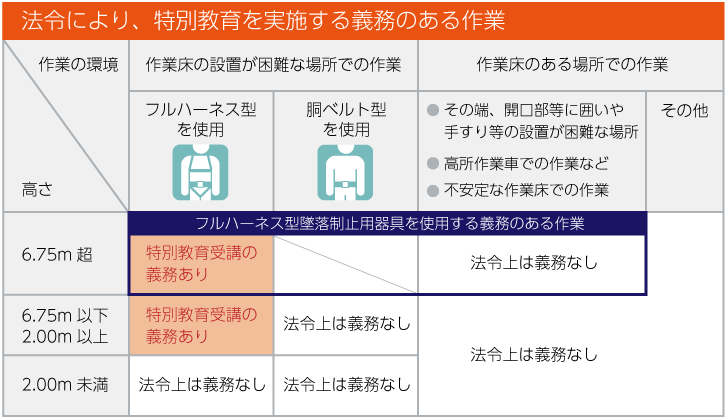
特別教育の必要な業務:高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち
フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
<対象となる作業例>
建築鉄骨の組立て、解体、または、変更作業 / 柱上作業(電柱等)、送電線架線作業
木造家屋等の低層住宅での作業 / 足場の組立て等作業の足場板設置、撤去作業 他
上記は一例ですが、一連の作業過程の一部で、作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合も特別教育の対象にも含まれます。
 今回の政令等改正の4つのポイント
今回の政令等改正の4つのポイント
1.安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変更
墜落制止用器具として認められる器具はつぎのとおりです。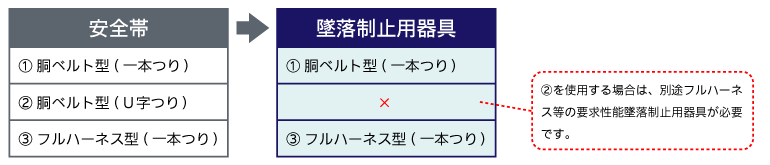
2.<6.75m>を超える箇所では墜落制止用器具は原則「フルハーネス型」を選定
2m以上の作業床がない箇所、または、作業床の端、開口部等で囲いや手すり等の設置が困難な箇所での作業の墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則となります。
フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本吊り)」を使用できます。(一般的な建設作業の場合は5m以上、柱上作業等の場合は2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。)
フルハーネス型は墜落を制止する際に身体の荷重を肩、腰や腿など複数個所で支持する構造の部品で構成され、背部に設けられたD環にランヤードを適切に接続できるものをいいます。(D環が胸部に設けられた仕様もあります)
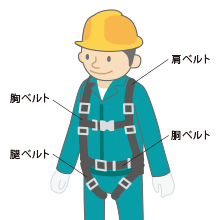
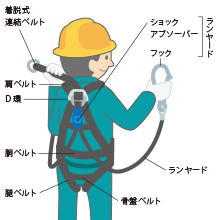
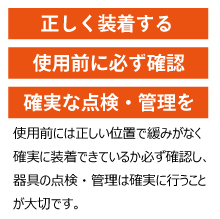
3.フルハーネス型安全帯の使用には「特別教育」が必要
墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務※を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間/実技1.5時間)を受けなければなりません。適用日は2019年2月1日からですが、適用日以前に受講することも可能ですので、お早めの受講をおすすめします。特別教育の内容は安全帯使用の経験、ロープ高所あるいは足場の組立て特別教育を修了しているかにより省略できる科目があります。
4.経過措置(猶予期間)
墜落制止用器具の構造規格が2019年1月頃に告示される予定です。現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型/フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日までです。

【 建設業事業主の皆様へ 】建設事業主等に対する助成金制度について
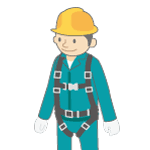
助成金を利用して受講料負担を少なくします。
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育は助成金の利用が可能です。
<注意点>平成30年6月19日以降に開始された実習のうち、賃金助成については1日3時間以上の実習が支給の対象となります。
・受講料の一部、受講期間の賃金の一部が助成されます。
・申請・受給の手続きやその他詳細はセンターへお気軽にお問い合わせください。
・助成対象の事業主については最寄の都道府県労働局またはハローワークでご確認ください。
助成金をご利用の際は、労働局またはハローワークに受給資格があるかどうか
お問い合わせの上お申し込みください。