林業を支える高性能林業機械を扱うために

日本の森林と林業について
日本は、国土面積の約三分の二を森林が占める世界有数の森林国です。
生物多様性に富む天然林、生活資材の供給源として利用される里山林、木材生産を目的とした人工林があります。
人工林は、森林全体の4割を占めその半数以上は50年以上が経過し、適正な伐採と再造林を着実に進めることが必要とされています。
育林、伐木・造材・集材などを担う林業従事者に目を転じると、長期的な減少傾向にあったものの近年は横ばいに転じています。林業の高齢化率は全産業の中では高い水準にありますが、一方で、若年者率(35歳未満の割合)は増加傾向で推移し、平均年齢の若返りが進んでいる産業といえます。
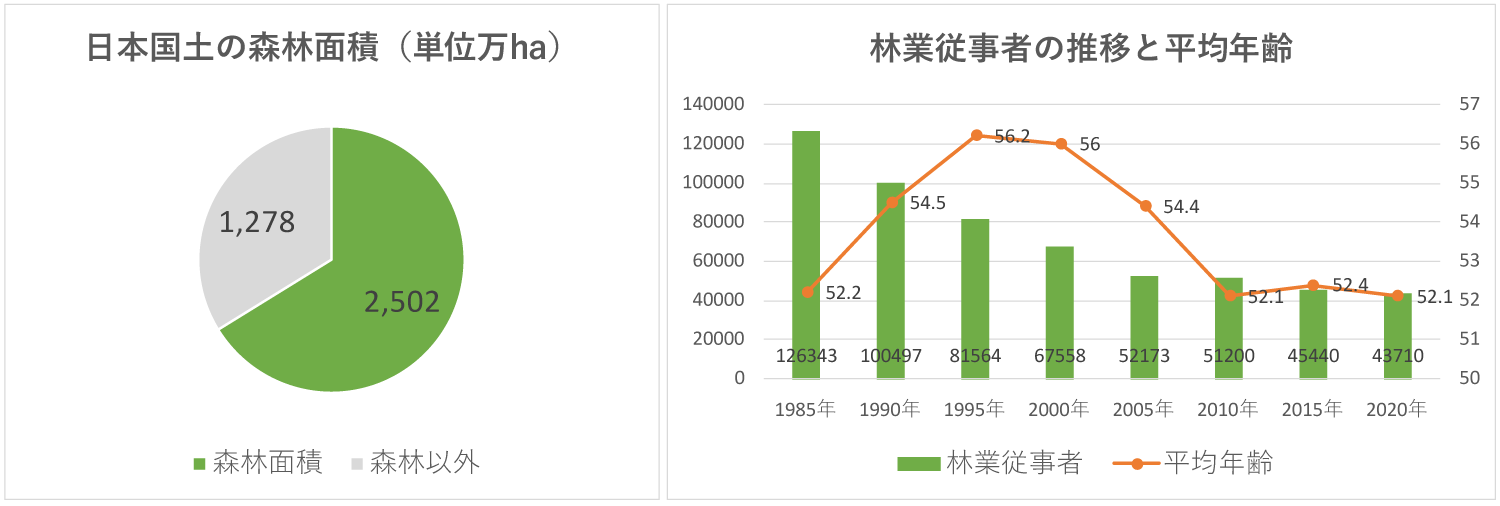
「令和6年度 森林・林業白書」農林水産省 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r6hakusyo/attach/pdf/250530-27.pdf をもとに作成
林業機械の種類と用途
林業の現場では、チェーンソー、刈払機などが用いられてきましたが、近年は伐木、集材などの機械化が進んでいます。
高性能林業機械といわれる「伐木等機械」「走行集材機械」「架線集材機械」などの林業機械は、生産性を向上させ、労働負担を軽減し、また、安全に作業が行えるように機能も進化し続けています。
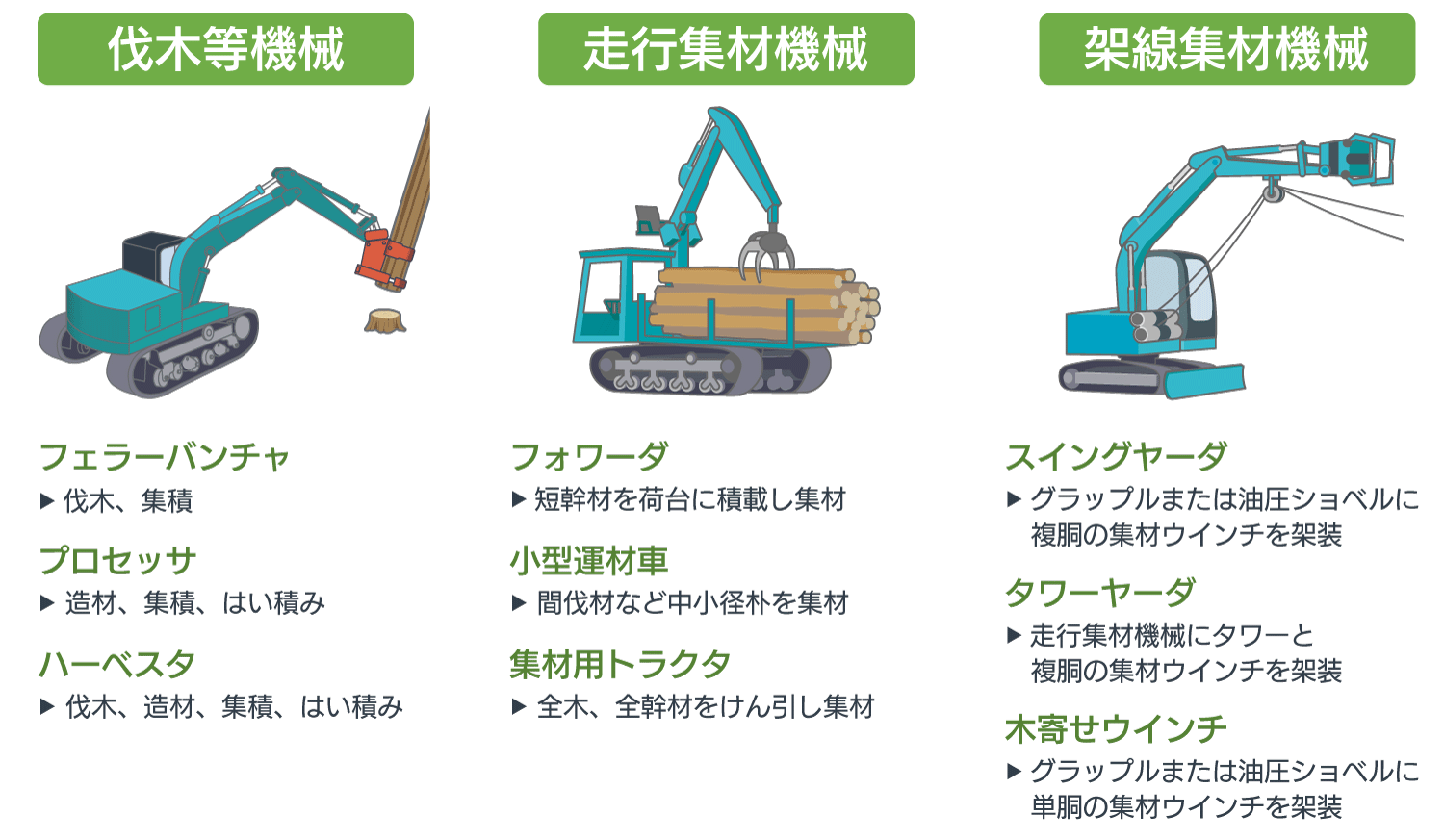
林業における労働災害
直近の労働災害による死亡者の数統計では、林業は全業種のうち約4%ですが、それでも年間に29件の死亡災害が発生しており、伐木作業中の事故が全体の7割を占め、その大半がチェーンソーによる伐木作業で発生しています。林業機械による災害は少ないものの、作業者への激突、機械の転倒などが発生しています。
厚生労働省の第14次労働災害防止計画では、伐木作業の災害防止を重点とした労働災害の大幅削減に取り組み、2027年までに林業での死亡者数を2022年と比較して15%削減することが指標として示されています。
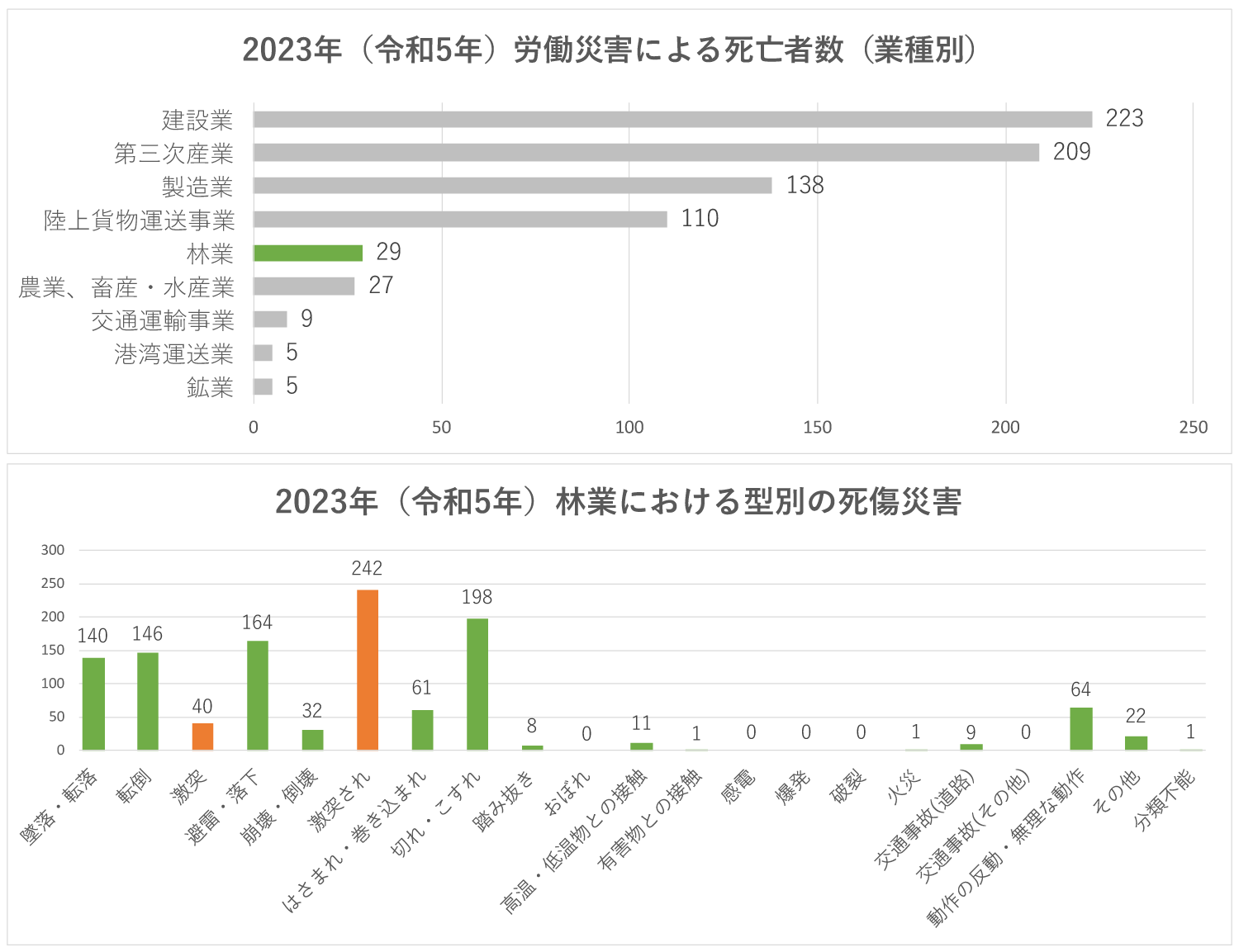
「令和5年における労働災害発生状況(確定)」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.htmlをもとに作成
労働災害防止のために
高性能林業機械の導入と林業機械の多様化・高度化が進み、従来のチェーンソーなどによる伐木作業に比べ効率的かつ安全に作業が行えるようになったものの、労働災害が増加傾向にあった平成26年には労働安全衛生規則の一部が改正され、林業機械運転は規制の対象となりました。
労働災害の事例では、事業者が業務に就く者に対して特別教育を行っていなかったことが原因として多く挙げられています。「伐木等機械」「走行集材機械」「架線集材機械」それぞれの運転に必要な特別教育を行い、労働災害の防止を図ることが大切です。
コベルコ教習所では、事業者の皆さまに代わり林業機械のうち「伐木等機械」「簡易架線集材装置」の特別教育を実施しています。
▼林業機械(伐木等機械)運転特別教育
[2aa1コース]2日間 12時間(学科6時間/実技6時間)
伐木等機械の実技では、フェラーバンチャを使用し木材の伐木・造材作業を想定した操作などを行います。
資格の詳細へ
▼林業機械(簡易架線集材装置等)運転特別教育
[2cc1コース]2日間 14時間(学科6時間/実技8時間)
簡易架線集材装置等の実技では、木寄せウインチを使用し地引き集材を行います。

